パラデータを提出する際は、基本的にはエフェクターを外したデータを提出します。その位は知っている方も多いと思います。
では、
クラブ系の定番の手法であるダッキングも外してしまって良いのでしょうか?
フィルターなどのパラメーターをオートメーションで動かしたトラックの場合は?
そういったことについて書かれているサイト等はなかった(見つけられなかった)ので、自分の体験を基にシェアしようと思います。
パラデータの基本
まずは基本から。
他のサイトで詳しく書いてあるページがありますので細かい話はそちらにお任せして、ポイントだけ押さえておきましょう。
音源やオーディオ素材がステレオでも、左右で全く同じ音が鳴ってるような物はモノラルで書き出した方が良いでしょう。モノラルはデータ容量の節約にもなります。
KickやSnare、Bass等が典型例。
DAWにファイルを並べて確認すると良い
1トラックずつ聴きながらエフェクターの切り忘れ等の確認をするのと同時に、波形の見た目で音量チェックやその他エラーが無いか視覚的な確認もできる。
そして、ここからが今回のポイントです!
サイドチェイン処理したトラックは?
サイドチェインというのは、エフェクトのかかり具合を別トラックの音を検知して調整する手法ですね。
パラデータの基本は「エフェクターをOFFにする」ですが、これは例外です。
トリガーも用意
エフェクトのかかり具合を別トラックの音で決めるという特性から、当然トリガーとなるトラックも必要となります。
最近では「Kickstart」のようなトリガーを使わないでダッキングを再現するようなプラグインもありますが、それでもやはりトリガートラックは必要です。トリガーがなかったらどうかけていいのか、「Kickstart」で簡略化しても良いのか解らないですからね。
至極当然です。
DryとWetの両方を用意
トリガーが解ったところでかかり具合は判断できません。
ですので、サイドチェインのかかったWetなトラックとかけてないDryなトラックの両方送りましょう!
もしかしたらWetの素材をそのまま使うことも考えられますが、そこはわかりません。機会があれば聞いてみたいと思います。
Filterなどのオートメーションを描いたトラックは?
こちらもWetとDryの両トラックを送りましょう!
オートメーションでパラメータを動かす際、どんな動きをするかが解らなければかけようがありません。一定の速度で動かすのか、加速度的に動かすのか、サイン波のような動きなのか等・・・。
こちらもWetとDryのどちらを使うのが多いのかはわかりません。
まとめ
その他にもWetとDryの両方を用意する必要がある場合があるかもしれません。そこら辺りは、今回の件を踏まえながらエンジニアさんの気持ちになって考えましょう!
ただ、疑問に思ったら迷わずエンジニアさんに質問するのが一番だと思いました。


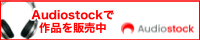










0 件のコメント:
コメントを投稿